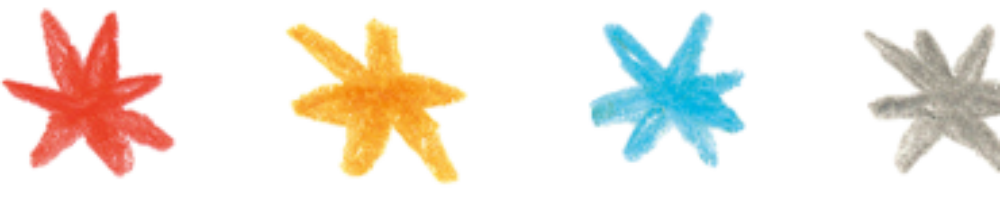石の中でも、特に薬になる石として書かれていたものをまとめてみました。
【 薬になる石 】
昔から、さまざまな鉱物が薬として利用されてきました。
漢方薬には、煎じ薬として鉱物が用いられています。
病気の原因が全くわからない古代には、動植物や鉱物を用いた治療が
宗教的・呪術的なものと結びついて行われていました。
中国では、マラカイトやアメジストは精神安定の薬と信じられ、細かく砕いた
ものを薬草と混ぜてお茶と一緒に煎じて飲んだといわれています。
3世紀ごろに出版された「神農本草経」には365種の天然薬剤が紹介され
その中には、鉱物も含まれています。
日本では、奈良・平安時代に中国から薬物書が伝来し、鉱物薬や動物薬が
多く用いられていたようです。
江戸時代には「炉甘石」と呼ばれる量亜鉛鉱を水で溶いて、結膜炎の治療に
目薬として使っていました。また、明ばんが血止め薬として利用されていたと
いいます。
古代ギリシャ人やローマ人は、ラピス・ラズリを強壮剤や下剤として使っていました。
アメジストは酒酔いを防ぐと信じられ、アメジストで作ったグラスで酒を飲んだといいます。
また、エメラルドには目を癒す力があると考えられていました。
その他
辰砂:鎮痛剤とてい用いる
金箔:自律真剣の亢進を鎮める、解毒効果がある、化膿症に用いる
滑石(タルク):胃炎、腸炎、腎炎に効果がある
赤石脂(カオリナイト):収斂剤として、止血効果がある、 下痢を鎮める効果がある、
強壮剤としても用いる
赤鉄鉱(ヘマタイト):補血のほか、収斂剤として止血効果がある、鎮痛剤、鎮嘔剤として用いる
硬石膏(アンヒデライト):解熱効果がある。下痢を鎮める効果がある、鎮痛剤として用いる